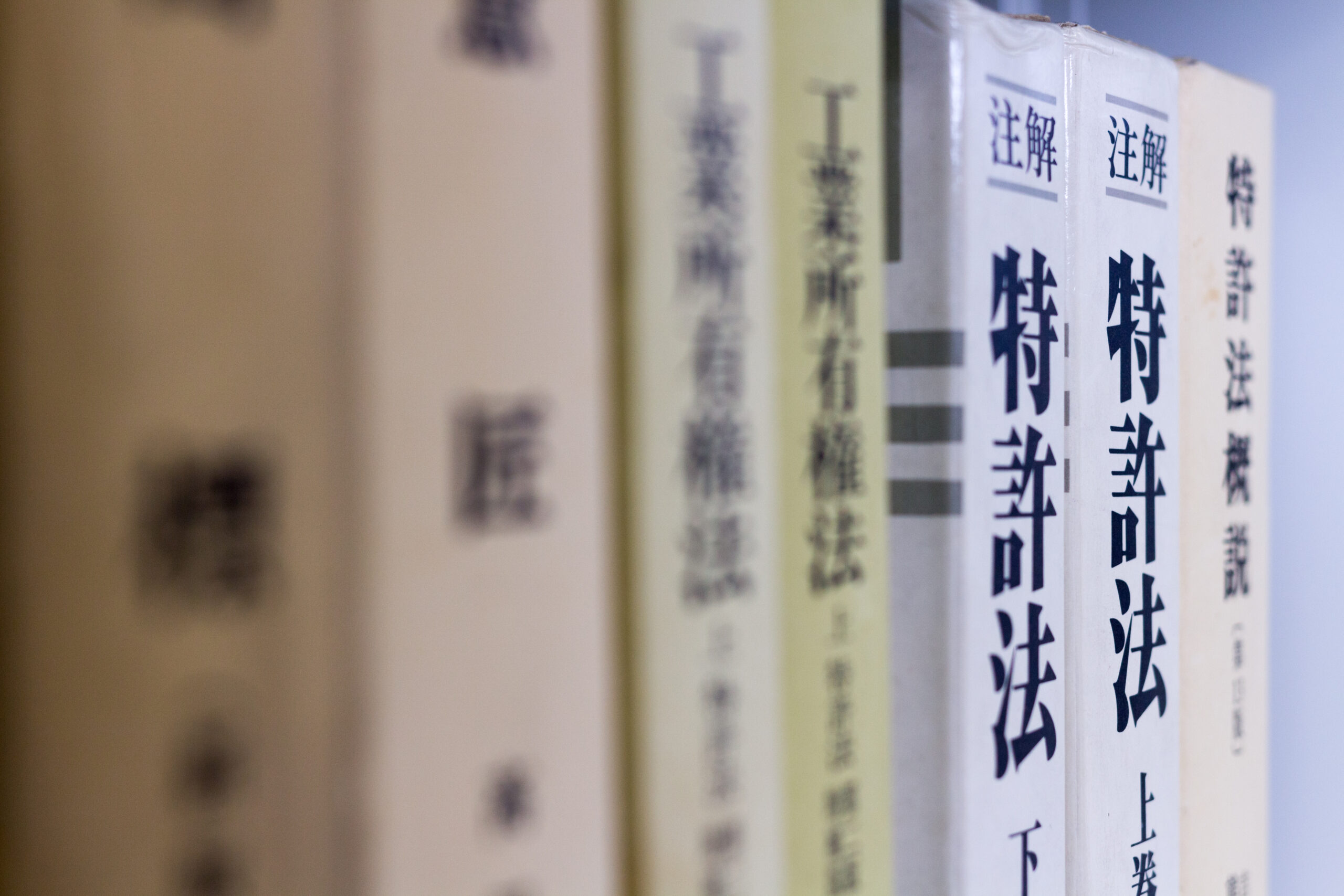令和5年6月から8月も様々な裁判例がありました。
その中から、今回は、知的財産高等裁判所の令和5年8月10日判決をご紹介いたします。
1 事案の概要
本件は、意匠に係る物品を「瓦」としその形状等を意匠(以下「本件意匠」といいます。)とする意匠権(令和2年10月2日に設定登録がされたもの。以下「本意匠権」といいます。)について、設計事務所等の第三者から、意匠登録の無効審判請求がなされ、特許庁が本意匠権を「無効」とする旨の審決をしたため、本意匠権者が当該無効審決の取消しを求めて訴えを提起したという事案です。
意匠登録には、いわゆる新規性の要件(意匠法3条1項)が必要ですが、新規性を喪失してしまった場合でも、一定の場合には新規性を喪失しなかったものとみなす規定(新規性喪失の例外規定。意匠法4条)が存在します。
2 主な争点
本件では、主として、
✓ 新規性が喪失したか(公然知られた意匠か)
✓ 仮に意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性が喪失した場合でも、新規性喪失の日から1年以内に意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をすることにより、その出願意匠について新規性を喪失しなかったものとみなす旨を規定する意匠法4条2項が適用されるか否か
といった点が争点となりました。
(なお、意匠法4条2項は、展示や見本の頒布などによって公開された場合の新規性喪失の例外を認める規定であり、例えば、マーケットリサーチ等の結果売れそうな製品等について、意匠登録を受けようとする場合に用いられる規定です。)
3 裁判所の判断
本件では、意匠登録出願前において、原告である本意匠権者(会社)の代表者が、被告である設計事務所の従業員に対して、本件意匠に相当する部分の意匠(以下「引用意匠」といいます。)が掲載されたパンフレット等がメールにて送信されており、その際に、内部資料、非公開資料などの表記もなく関係者に対する内部的なものであることを窺わせる事情がなく、また、設計事務所との間で引用意匠に関する秘密保持の合意もありませんでした。このような事情の下、当該メール送信によって、引用意匠が公然知られた意匠(意匠法3条1項1号)に該当し新規性を喪失するかが争いとなったものです。
裁判所は、ある意匠が他の者に知られた場合であっても、当該者が当該意匠について秘密保持義務を負う(契約がなくても、当該者との関係、当該者において知るに至った事項の性質及び内容等に照らし、当該者が当該意匠について秘密にすることを社会通念上求められる状況にあり、当該者がそのことを認識することができるときも、当該者が当該意匠について秘密保持義務を負う)と認められるときは、当該意匠は、意匠法3条1項1号にいう「公然知られた意匠」に該当しないとしたうえで、上記のような事情の下では、設計事務所は秘密保持義務を負うといえず、引用意匠は、上記メール送信により、公然知られた意匠(意匠法3条1項1号)に該当し新規性を喪失したと判断しました。
次に、新規性喪失の例外規定たる意匠法4条2項の適用を受けるためには、意匠登録出願前において公開され新規性を喪失した意匠について、対象となる公開の事実を記載した法定の証明書を出願にあたって提出する必要があります(意匠法4条3項)。
本件では、上記メール送信の数日後に、引用意匠の公開行為(市に対する説明会におけるプレゼンテーション)がありました。この点、被告である設計事務所の従業員から原告である本意匠権者(会社)の代表者に対して、当該プレゼンテーションにおいて引用意匠を含む「瓦」について説明したいので、事前に市に対して「瓦」のサンプルを送っておいてほしい旨の依頼があり、これを受けて、原告である本意匠権者(会社)の代表者が、市に対して資料を提供するともに、被告である設計事務所の従業員に対しても、上記メール送信がなされたものでした。他方で、プレゼンテーションは設計事務所の代表者の一人が行ったものでした。このような中、本件では、上記公開行為(プレゼンテーション)については、法定の証明書に記載があるものの、上記メール送信については、法定の証明書に記載がありませんでした。このため、法定の証明書の提出に不備があり、意匠法4条2項の適用を受けられないのではないかが問題となりました。
裁判所は、本件のように、ある意匠の公開行為が複数存在する場合において、当該意匠につき意匠法4条2項の適用を受けるためには、原則として、全ての公開行為について同条3項に定める手続を履践する必要があるが、例外的に、ある意匠が同項に定める手続を履践した公開行為及び当該公開行為と実質的に同一であるとみることができるような密接に関連する公開行為によって公開された場合には、全ての公開行為について同項に定める手続を履践しなくても、当該意匠について意匠法4条2項の適用があるとしました。そのうえで、上記メール送信は、原告である本意匠権者(会社)の代表者が被告である設計事務所の従業員に対して行ったものであるのに対し、上記公開行為(プレゼンテーション)は、被告である設計事務所の代表者の一人が市長らに対して行ったものであるなどの本件における事情の下では、両者は、行為の主体、客体、内容及び態様を全て異にするといえ、上記メール送信が上記公開行為(プレゼンテーション)と実質的に同一であるとみることができるような密接に関連する行為であると評価することはできないとして、上記メール送信について、法定の証明書に記載されていない以上、本件では、意匠法4条2項の適用を受けることはできないと判断しました。
以上のとおり、裁判所は、本意匠権者の無効審決の取消しの主張を認めず、特許庁が本意匠権を「無効」とする旨の審決を維持しました。 本件は、事例判断ですが、意匠権における新規性喪失の判断や新規性喪失の例外規定たる意匠法4条2項の適否の判断について、参考になる部分があると思われましたので、ご紹介する次第です。