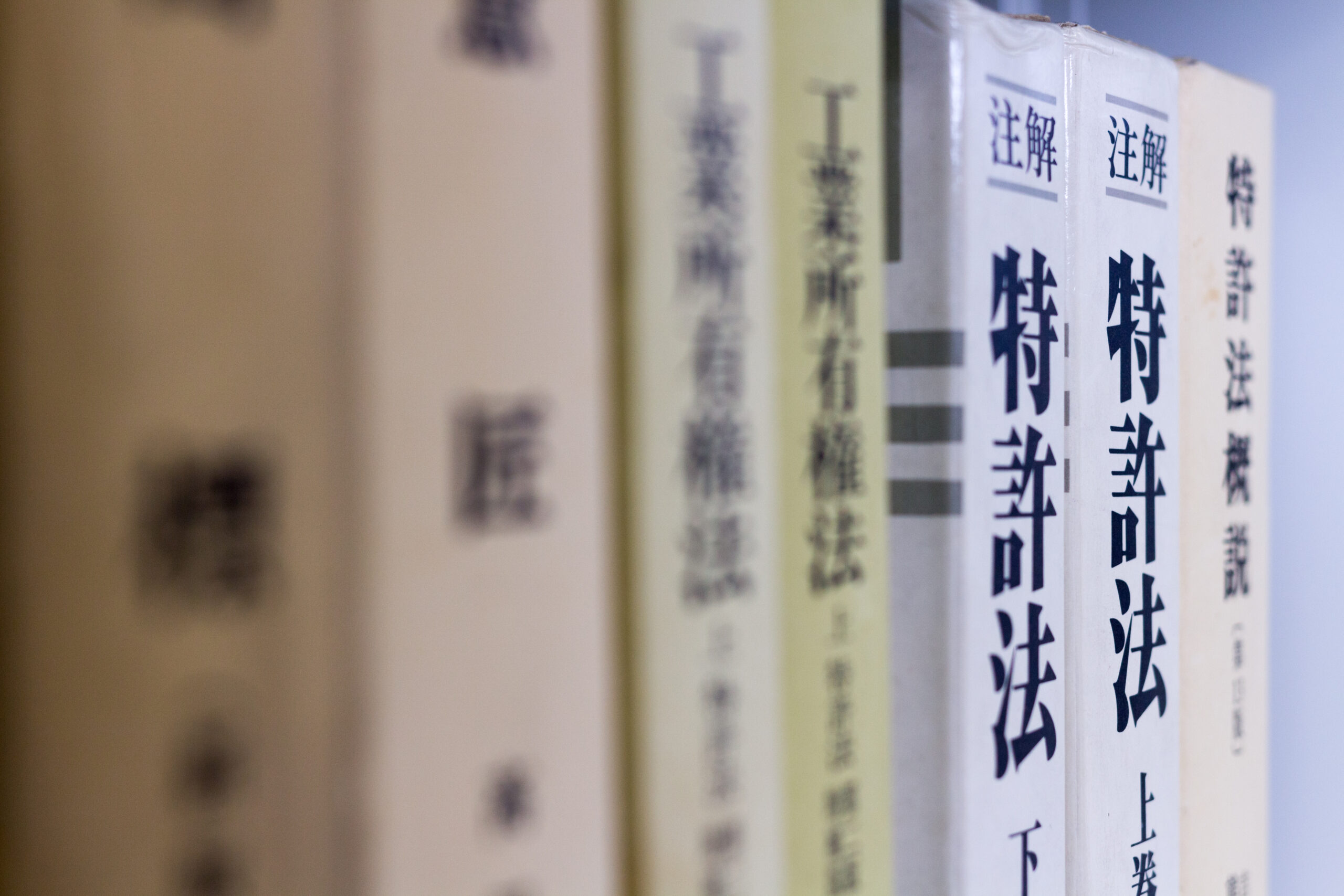You Tubeに、無断で、字幕やナレーションを付け10分程度に編集したファスト映画を投稿した人物に対して、CODA等の会員企業13社が原告となって、損害額20億円のうちの5億円を求めた事案が認容されました。
違法投稿者は、少なくとも700万円の広告収入を得ていたとされ、社会的な関心も集めていました。損害額の立証にあたっては、著作権法114条3項に基づき、消費者が映画を購入するにあたりYou Tubeに支払う金額やプラットフォーム手数料等を基礎として、使用料相当額が算出されています。
それでは、今回は、You Tube上の著作権侵害の通知制度を利用した場合に不法行為が認められることを判示した裁判例をご紹介します。
問題となった裁判例は、You Tubeへの投稿者は、正当な理由なく投稿動画を削除されないことについて法律上保護される利益を持っているとしたうえで、侵害通知制度の要件として、①著作権を侵害すると考える投稿の説明に加えて、②通知者自身が著作権者等であること、③投稿者によるコンテンツの使用が法律で許可されていないことを確信していること、④通知が正確であることを確認した上でこれを行うことを求めており、また、⑤不正に制度を利用すると、アカウント停止等の可能性を示唆していること等に照らし、注意義務を尽くさずに漫然と通知を行う行為は、不法行為を構成するとしました。
この事案では、警告制度に基づき削除された動画が、著作権を侵害する事情がなかったことや、そのことについて、通知を行った人物が独自の見解に基づいて著作権侵害となると考えていたこと、自らが著作権者であることの検討をしなかったこと、著作権侵害がない蓋然性があると認識した上で行動したこと等から、必要な注意義務を怠って漫然と通知を行ったと判断されました。
著作権には登録制度がなく、また、著作権として保護される表現物と保護されないアイデアの区別は難しい部分もあるので、安易に(濫用的に)通知制度を利用しないよう注意が必要であることを改めて確認させられる裁判例でした。