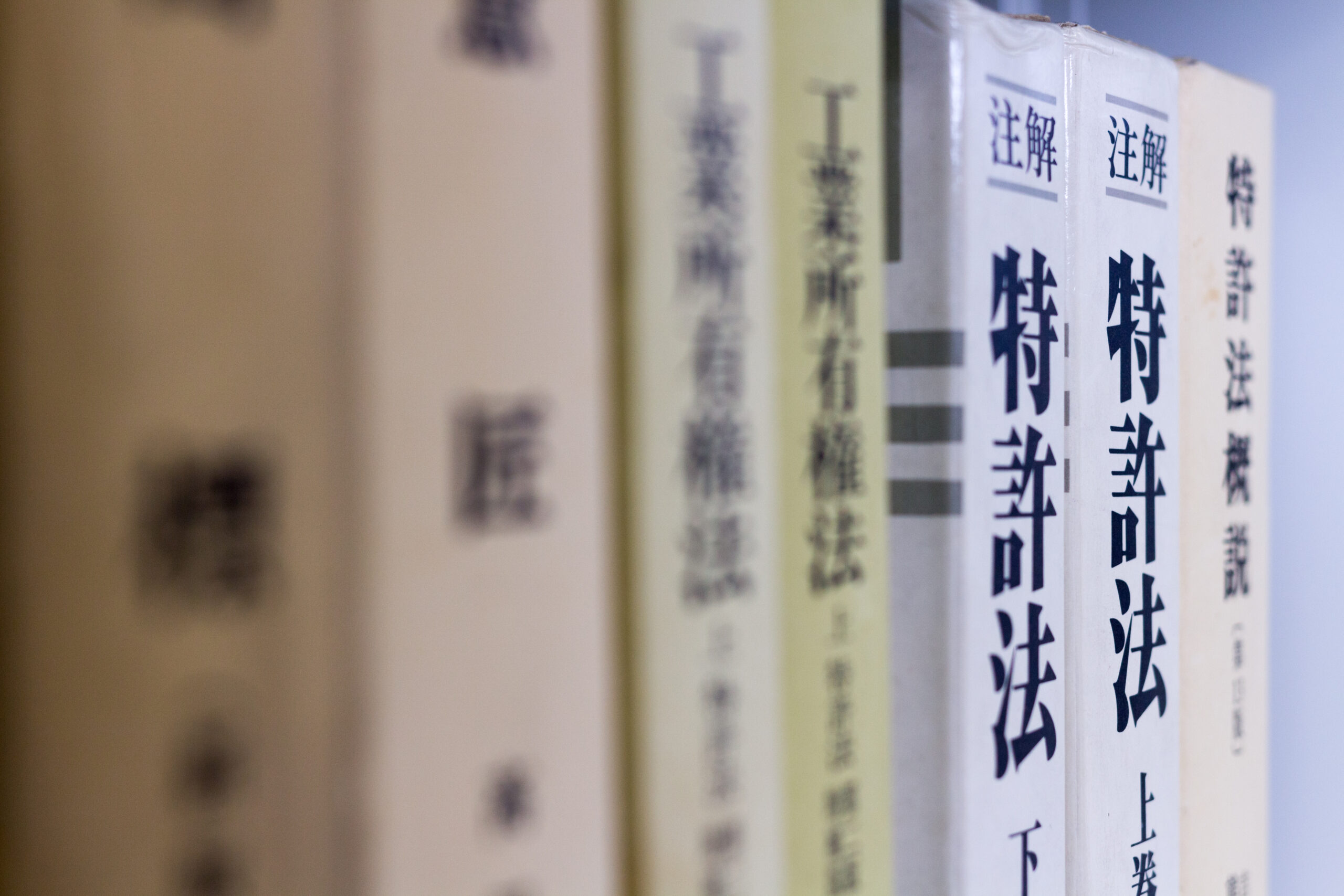2021年改正のプロバイダ責任制限法が2022年10月1日に施行されました。今回の改正は、①発信者情報の開示請求にかかる新たな裁判手続の創設と、②開示請求範囲の見直しが大きな目玉でした。特に①の非訟手続創設により、申立人は、従来2つの手続が必要であったところ、同じ手続内で、コンテンツプロバイダ(SNS事業者等)に対する開示命令申立を行うとともに、経由プロバイダ(通信事業者等)に対する開示命令申立をすることができるようになり、迅速に開示が行われることが期待されています。
なお、総務省が公表しているQAにおいて、施行日前に起きた権利侵害事案であっても、改正法に基づく開示命令の申立てを行うことは可能であるとされています。このこともあってか、施行日前の知的財産権に関する発信者情報開示請求事件の判決は減少しているようでした。
また、今月24日、最高裁は、音楽教室における生徒の演奏が「公衆に直接…聞かせることを目的として…演奏」(著作権法22条)にあたるか否かが問題となった事案(仮にあたるとすれば、音楽教室の運営主体は、JASRACに対して許諾料を支払う必要があります)において、生徒による課題曲の演奏は、生徒が、演奏技術等の向上を目的として手段として行われるものにすぎず、受講料の支払いも演奏技術等の享受を受けることの対価であって課題曲の演奏の対価ではないとして、生徒の演奏に関して、音楽教室が著作物の利用主体とみることはできない(すなわち、公衆に直接聞かせることを目的とした演奏と評価できない)と判断しました。
今回は、漫画家(原告)が、違法な海賊版ウェブサイトである漫画村に広告を出稿していた広告代理店(被告ら2社)に対して、損害賠償請求を求めた事案をご紹介します。
まず、漫画村の運営者が、原告の漫画を無断で掲載した行為については、原告の著作権(公衆送信権)侵害に該当するところ、本件では、被告らが、漫画村への広告主を募り、漫画村の管理者に対して広告料を支払ったこと等により、上記公衆送信権侵害を幇助したといえるかが問題となりました。
著作権法には、漫画を複製したり、複製データをネットで配信するといった複製権侵害・公衆送信権侵害といった直接的な侵害行為以外であっても、一定の類型に該当する場合には著作権侵害行為とみなす旨の規定が存在しますが(113条)、これに該当しない場合でも、著作権侵害となる場合があることが裁判例で判示されています。
裁判例においては、例えば、飲食店等の経営者が、客や従業員による歌唱やカラオケ装置による歌詞・楽曲の上映又は再生をする行為が、音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り、演奏権ないし上映権侵害に当たると判示しており、その上で、カラオケ装置のリース業者が、JASRACとの間で著作物使用許諾契約を締結していないカラオケ店に対して、リース契約を締結してカラオケ装置を引き渡す行為は、幇助行為に該当すると判断しています。
本件控訴審において、控訴人(広告代理店)は、広告に関する一連の行為は、漫画村の運営者に対して著作権侵害行為自体を直接誘発し、又は促進するものではないから幇助行為には該当しないと主張しました。しかしながら、東京高裁は、漫画村は広告料収入をほとんど唯一の資金源としているという実態があることを踏まえると、当該行為は、違法アップロードした漫画の掲載を継続するとともに、さらにアップロードする対象を追加することを直接誘発し、又は促進するものであるとし、公衆送信権侵害の幇助行為に該当すると判断しました。
また、損害額の認定にあたっては、114条1項の推定規定が用いられました。受信複製物の数量の認定にあたっては、漫画村の特性上、連載漫画については一度の訪問で複数巻を閲覧することが十分に考えられる一方で、途中まで試し読みして閲覧を止めるようなことも考えられること等を裁判所は指摘したものの、個々の訪問者の利用の仕方の詳細について明らかにすることは不可能と述べた上で、「少なく見積もったとしても」、受信複製物の数量は、漫画村訪問者数の5割を下回ることはない(換言すると、「受信複製物」の数量をPVの約5%、二度の訪問あたり1冊にとどめること)と認定した点も注目ポイントです。
本件は、著作物の利用行為を物理的に容易にする行為ではなく、サービス資金を提供する行為が幇助行為に該当するとした点で、実務上も参考になると思いますので、ご紹介いたしました。