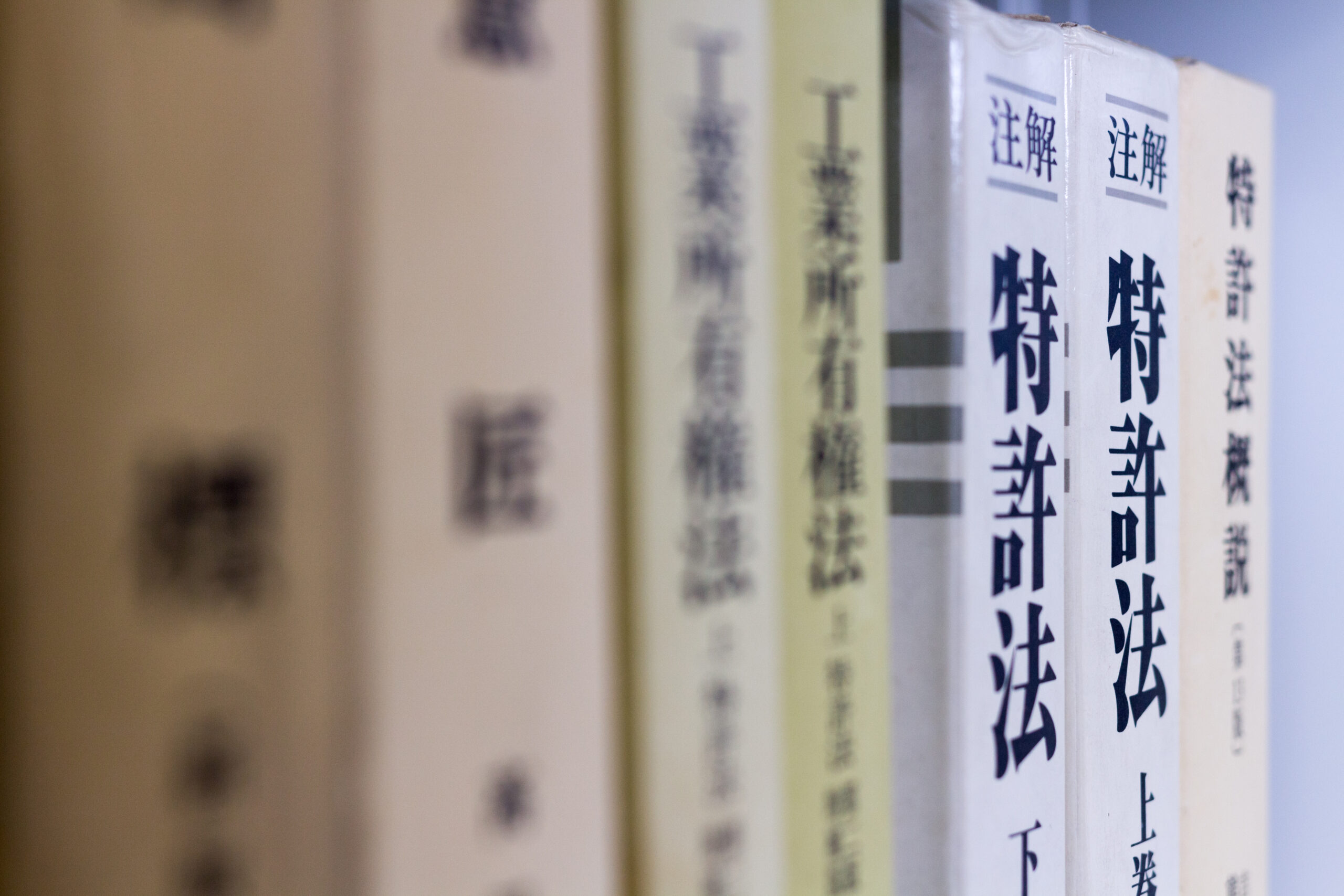令和3年11月から令和4年2月にかけて、様々な知的財産法に関係する判決が出されました。
事案1
漫画家が、漫画村にサーバーを提供していた米国会社に対し、漫画村の運営に関与していた発信者の情報を開示するよう求める訴訟を提起しました。原審は、漫画家は、①米国会社から「IPアドレスやタイムスタンプ、ユーザーの電子メールアドレス」の任意開示を受けていたこと、②漫画家サイドが、①によりサイト運営者と思われる人物を特定できたと発言していたこと、③サイト運営に関与した4名が逮捕・起訴されており、氏名が判明していたことから、発信者情報の開示を受ける「正当な理由」はないと判示しました。しかし、控訴審は、逮捕起訴された人物が、被疑事実に関係する違法アップロードをした以降も漫画村の運営に関与していたのかは不明であることや、関与者の全容が解明されていないこと、任意開示を受けた情報からでは、発信者を特定できなかったこと等から、発信者は特定されておらず、「正当な理由」があるとして、原審を覆しました。漫画村に関する訴訟は、令和3年のプロバイダ責任制限法改正にも大きな影響を与えています(改正法は、2022年10月までに施行されます。)。
事案2
続いて、こちらも有名なPUMA=SHI-SA事件に関する判決のご紹介です。
プーマ社が、「SHI-SA」等の文字とシーサー風の動物の図形(四足動物が右側から左上方に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれたもの)を組み合わせた商標権(以下「本件商標権」といいます。)を有する被告に対し、本件商標権を無効とすべく審判請求を行ったところ、特許庁は原告の請求を認めない旨の審決を行いました。そこで、原告は、当該審決の取消しを求めて訴訟を提起した事案です(ちなみに、被告は、無効審判の審理中に、本件商標権を放棄していますが、原告の請求が認められると、過去に遡って本件商標権が無効となりますので、本件商標権が放棄されたとしても、審判や訴訟は終了しません。)。
原告は、本件商標権が、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」(商標法4条1項15号)にあたるとして無効を求めましたが、これを理由として無効を求めることは、「不正の目的で商標登録を受けた場合」を除き、商標登録から5年経過後はできないものとされています(商標法47条1項)。そこで、本件では、「不正の目的で商標登録を受けた場合」にあたるか否かが主な争点になりました。
知財高裁は、まず、本件商標とPUMA社の商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても異なり、本件商標とPUMA社の商標が同一又は類似の商品に用いても出所の誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないから、両商標は類似していないとしました(過去の知財高裁判決でも同旨が判示されています)。そのうえで、需要者が、本件商標のシーサー風の動物の図形はPUMA社の商標を模倣したものと連想、想起するからといって、PUMA社の商標の顧客吸引力にただ乗りする等の不正な目的が認められないと判示しています。原告は、無効審判手続において、被告が原告の請求を事実上認諾している旨の陳述を行ったことも主張しましたが、無効審判手続が職権探知主義を採用しており、自白法則や処分権主義の適用がないことから、この事情は斟酌できないと判示しています。
一連のPUMA=SHISA事件は、原被告の商標が文字と図形を組み合わせたもの・図形のみのもの、請求理由が公序良俗違反(4条1項7号)、先願(4条1項11号)や本件の15号等、レパートリーが多く、商標法の基本的な部分の理解に役立つ事件集かと思いましたので、ご紹介させていただきました。